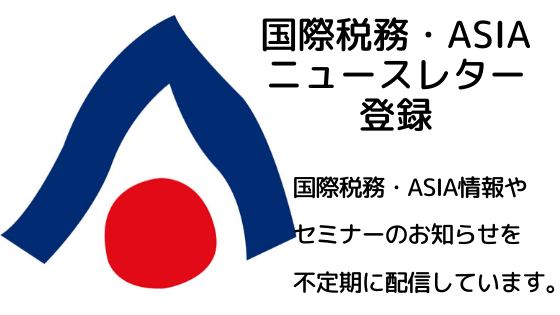LIBRARYライブラリー
CHINA 海外派遣社員 源泉課税
【CHINA】中国駐在員 帰任・赴任時の個人所得税の留意点について
2025.03.31
※ 本ブログはBUSINESS PARTNER株式会社BPアジアコンサルティング の原稿提供により掲載しております。
異動の季節となり、新たに中国に赴任される方、日本に帰任される中国駐在員の方も多いと思います。このように年度の途中で赴任、帰任をすると、留意すべき注意点が多数発生します。本書では赴任・帰任それぞれの日本・中国での個人所得税の留意点について解説します。
4月より中国に赴任される方:
<日本にて>
出国前には準確定申告が必要だ、とお聞きになられた方もいると思います。準確定申告とは出国までの所得を申告するもので、この場合所得が1~3月分しかない=年収が小さいため、通常よりも納税額が小さくなる傾向にあります。
しかし出国前は何かと忙しく、申告せぬまま出国してしまった方もいると思います。しかし準確定申告は全てのケースで必要なのではありません。勤務先の給与しか所得がないような一般的なケースでは勤務先にて年末調整が行われ、準確定申告は不要ですのでご安心ください。
<中国赴任後>
4月以降の給与は中国で納税することになります。ここで給与の一部を日本本社が負担・支給する企業もありますが、この日本本社支給給与も中国個人所得税の課税対象となります。これは支給地ではなく、どこで発生した源泉(中国での勤務で発生)なのかで納税地が決まるためです。
従って日本支給給与は中国で納税することで完結し、日本での課税は何ら不要となります。
そして中国駐在開始後、中国の居住者として個人所得税を毎月申告納税するのですがここで留意点があります。
中国では年間6万元の基礎控除を受けることができるのですが、実務ではこれを12分割した月5千元を月次申告で控除します。
従って4月に赴任した場合、5千元×9カ月=45千元しか控除していないことになり、年間限度額6万元との差額15千元は確定申告で調整(税還付)する必要があります。
一方、もし駐在開始が7月以降、すなわち駐在初年度の中国滞在日数が183日未満の場合、初年度は中国の非居住者として毎月申告納税することになります。非居住者の場合、中国支給の給与のみが個人所得税の課税対象となり、日本本社支給給与は課税対象外になります。
通常は日中支給給与全てが中国の課税対象となるため、間違えて駐在初年度から日中支給給与全額を申告してしまっている企業も見受けられます。
注:非居住者の場合の基礎控除は、毎月5千元のみであり、居住者のような年間6万元との調整はできません。
以上の通り、駐在初年度は駐在開始が上半期(1-6月)なのか、下半期(7-12月)なのかにより、通常とは異なる調整や留意点がありますので、この点充分にご留意ください。
<その他>
4月1日で中国駐在の辞令が出ても、駐在ビザ、就業許可及び居留許可の取得を完了するまでには一定の時間がかかります。一方現地法人から給与支給を受けるには居留許可の取得を完了している必要があります。
このため、現地法人の給与支給日までに居留許可が取れていない場合、現地給与の支給は保留し、日本本社が立替支給する等の調整が必要となります。
また日本の住民税について、これは1月1日の住所で課税が決まるため、4月以降中国に駐在しても2024年度の住民税の納付(2025年6月以降)は必要となりますのでご留意ください。
3月で日本に帰任される方:
<中国にて>
例えば、1月の時点で(3月に)帰任することがわかっていたため、1~3月の中国給与を非居住者として申告をし、その課税対象も中国支給給与分のみとしていた場合は、特段の調整は不要です。
しかし辞令は突然やってくることも多く、1月からも居住者(3月帰任をまだ知らない)として申告をしていた場合、個人所得税を過大納付していたことになります。
これは、前述した通り非居住者の課税対象が中国支給給与のみであるため、居住者として日中支給給与全てを申告納税すると、日本給与分を過大に申告納税していることになるためです。
この場合は確定申告をすることで過大納付した個人所得税の還付を受けることができます。但し還付金は駐在員本人の中国の銀行口座に振り込まれますので、駐在員は帰任となっても中国の銀行口座を閉鎖しないようにご留意ください。
また、もし7月以降に帰任となった場合、帰任年度は居住者(183日以上)となります。従って前述の赴任者と同様、毎月の基礎控除(5千元×滞在月数)と年間控除額の6万元との差額を確定申告により還付請求することができますので、この点についてもご留意ください。
<日本にて>
4月以降の給与は日本の課税対象となり、通常は会社が源泉徴収(及び年末調整)をするのでこれで完結します。なお、帰任後は日本の居住者となりますが、日本は全世界所得課税のため、1~3月の中国給与も日本で申告納税しなければならないのでは?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかしこの場合、1~3月は日本の非居住者であり、この期間の中国給与は日本の課税対象外となります。日本での申告は不要ですのでご安心ください。
<その他>
3月末で中国駐在終了、日本帰任の辞令が出ても、実際には引越や引継等のため、日本に帰国するのが4月以降の○○日になる、という方が大多数と思います。ここで4月1日以降の中国滞在期間中における給与の納税地が問題となります。
確かに3月末から4月以降にかけて連続して中国に駐在しており、見た目は同じ駐在員のように見えます。しかし中国の駐在はあくまで3月末までであり、4月1日以降は日本本社の社員が、いわば中国に出張に来ているだけと分けるべきですので、中国個人所得税の課税対象は3月までの給与(注)となります。
注:4月1日以降はいわゆる183日短期滞在者の免税規定が適用されます。よって4月1日から帰国日までの数日~十数日の給与に対する中国での個人所得税は免除されます。
本件については、何を持って3月末までを駐在員、4月以降を日本本社から出張している社員なのかを証するのか、という実務上の問題も発生します。これは日本本社からの辞令、また4月以降の日本での課税(源泉徴収)や、工作許可、居留許可の取り消しなどをもって説明します。
これは赴任者も同様で、4月1日から中国駐在の辞令を受けていますが、その準備として3月に中国入り(出張)している方も同様です。
一方日本の住民税について、1月1日に日本の住所が無いため、帰任年度の住民税は不要です。当年度の住民税は翌年6月から納付するため、帰任後2年程度は住民税の納付が不要となります。
なんだか得したように見えるかもしれませんが、なにも得をしているわけではありませんので給与・納税資金の管理には十分ご留意ください。
参考:
株式会社BPアジアコンサルティングでは、中国駐在員の中国個人所得税の申告納税代行業務を行っております。
当該業務では上述の問題点の整理や中国現地法人から駐在員給与情報を隔離できるなど、様々なメリットがございますので、ご関心ありましたらいつでもお問い合わせください。
この記事について、中国進出のお問い合わせは CONTACT までどうぞ。